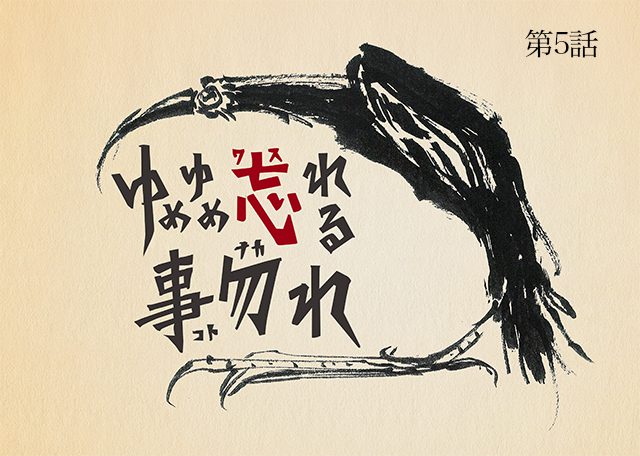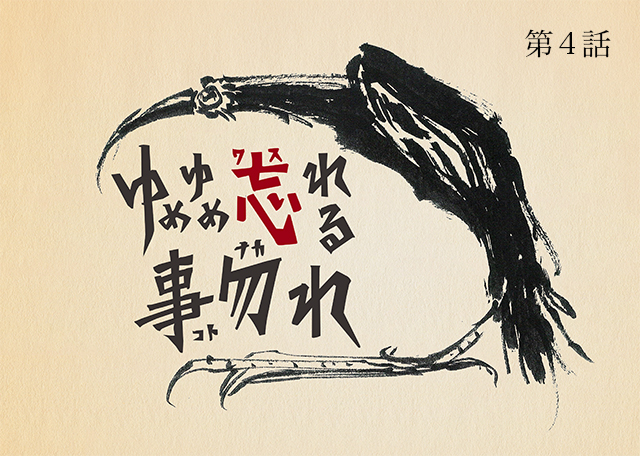再びあの少女、さざきがいるあの世とこの世の狭間から現世に舞い戻った九郎。強い決意とともに古民家へ向かう。そこで出会うはずの男を助けるために。九郎は烏丸から二人を救う事が出来るのか。男との出会いから物語が多きく動きはじまめる第5話。
第二章 忘れることはできない 第5話

三回目ともなると流れるように子供を背に乗せ、駆けていける。
足首をひねらぬように、負ぶった子供を落とさぬように、気絶するほど体力をなくさぬように気をつける。
木々の隙間から零れる満月の明かりで足元が見えるのが唯一の救いだった。
それでもあの血にまみれた白い腕が背後から髪を引っ掴んできそうな気がして、時々振り返ってしまう。
怖くて怖くてたまらない。ぎゅうと首に巻きついた手と、背に伝わる暖かい体温が無かったらとっくに泣き叫んだいただろう。
早く早くあのさびれた家に着きたい。それだけを念頭に九郎は走った。
やがて民家へと辿り着いた。
薄っぺらい木の戸を叩く。
「お願いします! ここを開けて下さい! 怪しいもんじゃない!」
ずり落ちかけている子供を背負いなおし、九郎が抑え気味に叫んだ。
だが、戸は開かない。
しつこいくらいに扉を力任せに叩く。
開かないはずはない。あの時確かにこの戸が開いたんだ。
早くしないと奴が来てしまう。
「お願いです! おっかない奴に追われてるんだ!」
九郎が半分悲鳴のような、泣きべそのような叫びをあげながら戸を叩いていると、唐突に戸が開いた。
つんのめった九郎は思い切り鼻を正面の硬い何かに打ちつけた。
「うるさい」
鼻を抑えていると、唸り声のような低い声が頭上から降ってきた。
大柄な男が頭を掻きながら立っていた。
ぶつけたのはどうやら男の壁のような胸板らしい。
「子供もいるじゃないか」
口をへの字にして男が言った。皺の寄った眉間といい、厳しい目つきといい、厳つい体格といい、とても近寄りがたい雰囲気が出ている。
九郎はあっけにとられて男を見上げていた。
「は、はい」
「とにかく寝かせろ、奥にゴザがある。この子は怪我してるのか?」
灯明がついているのか、仄明るい奥の座敷を指さしながら男が言った。
「しては無いと思い、ます」
「お前は」
「大丈夫、その、ありがとうございます」
前に烏丸から助けてくれて。とは言えなかった。
「礼には及ばん」
「お邪魔します」

九郎は半分苔の生えたあがりっぱなに入った。かびの臭いがどんよりと部屋を覆っている。
「俺はただの通りすがりの浪人だ。敬語はやめろ」
「わかった……」
奥のゴザにうつらうつらしている子供を寝かせると、九郎は男の座っている居間に正座した。
毛羽立った畳がちくちくと痛いが、腐っていないだけましだ。
「別にとって食うわけじゃない。そんなにかしこまるな」
そのくせ男はきっちりと背筋を伸ばして正座している。
年の頃は九郎よりも上だろう。
擦り切れてはいるが仕立ての良い着物を纏った長身に、鉄片を叩き込んだ様な筋肉の手足。どこもかしこも鍛え上げられた体はまるで仁王像のようだ。
いかにも厳つい印象与えるが、鼻や顎が大きいためにどことなく愛嬌がある。
この男の性格が信頼できるのは、とうに九郎は知っていた。身を挺して見知らぬ子供を庇う男に悪人はいない。今だって、気にかけるように何度も子供に視線をやっている。
男が、ふと子供から九郎に視線を向けた。
「お前、どこかであったか」
「え! いや、初めて会いました、じゃない、会ったはずだ」
「そうか。その気弱そうな面に見覚えがあったような気がしたのだが……」
男が眉間にしわを寄せて言った。
その真面目くさった顔に毒気を抜かれそうになる。
「失礼な。って違うそんな場合じゃない、おっかない奴が来るんだ! とりあえず火を消してくれ」
男が灯明を吹き消すと、九郎は小さな声で今までのことを語った。
近くの小菅村に住んでいること。その村が野盗に襲われていること。烏丸というその野盗の首魁(しゅかい)に追われていること。
「もう少ししたらそいつがこの家の前に来ちまう。おれがとりあえずあいつを撒くから、その間ここであの子を預かっててもらえないか?」
男は腕を組みながら、唾を飛ばしながら話す九郎の言葉に耳を傾けていた。
「お願いだ。信じてくれ、あんたが良い人だってことは分かってる、頼む」
「あの子はお前の子か?」
「違う、途中で見つけただけだ」
「ではなぜ、そんなにも必死に助けようとする?」
九郎は猛禽のように鋭く光る眼から逃げるように目を伏せた。
「あの子に助けてって言われたから。助けてって言われると弱いんだ、おれ。捨て子だったとき、自分がそれ言って爺ちゃんに拾ってもらったもんだから」
「それだけなのか?」
驚いたような声が頭の上から降ってくる。
「そうだよ。自分でもちょっとおかしいとは思ってんだけどさ。なんでもしてやりたくなっちまうんだ。体が勝手
に動いちまうんだよ」
「それは、随分難儀だな」
「……だからこんな目にあってる」
「そうか。……む?」
微かに何かが土を踏む音が聞こえた。
「奴だ!」
「しっ!」
尻を浮かす九郎を、男が制した。
徐々に足音が大きくなっていく。

男は音もなく立ち上がると破れた障子の穴から外を覗いた。
「あ、あれ、いない、あいつ、いない」
微かに粘つく様な、男にしては高い声が聞こえた。
九郎は座ったまま身動きも出来ず、汗をかきつづけていた。
唐突に小鷹の目の前三寸の所に白刃が現れた。
「ひっ」
「耐えろ」
悲鳴を漏らした九郎を、小声で窘めると男は猫のように静かにしなやかに後ずさる。
「いない、いない、いない、なあ」
何度も何度も壁から白刃が突き出る。
悲鳴を必死で押し隠す九郎に対して、男は静かに息を殺していた。
白刃が突き出るのが止まると同時に、どんと壁が揺れた。
びくりと九郎の身体が跳ねる。
恐らく烏丸が殴りつけたのだろう。
それから何度も何度も、壁に衝撃が走った。
古ぼけた家全体に振動が伝わり、ぱらぱらと砂埃が男たちの上に落ちる。
頼むから、ちびが今起きだしませんように。それだけを祈る。
「……いいや。きんきらの仏さま、のとこ、帰る、帰ろう」
永遠にも思えるその数瞬の後、呟き声を最後に足音は遠ざかっていった。
完全に足音が消えると、男が灯明に再び火をつけた。
弱いが暖かい光は心を緩めてくれる。九郎は詰めていた息を大きく吐きだした。
男がどかりと九郎の前に座った。埃が舞う。

「今のがそうか」
「げほ、ああ、そうだ。あいつが烏丸だ。おれの村を焼いた糞ったれだ」
九郎が埃にむせながら言った。
「奴は行ったし、今のうちにおれはあの子を連れて湖のほうに逃げるよ。ごめんな、邪魔して」
「……奴を追う」
よどんだ空気の中に男の重々しい声が波紋を作った。
「今何て言った?」
「奴を追わねばなるまい。まだ、村に生きている者がいるやもしれぬ。彼らが殺される前に、奴を誅殺する」
「は」
九郎はあんぐりと口を開けた。
せっかく死を回避させたというのに、何を言い出すのか。
「無理だ! あいつは強い! 仲間もいるんだ! 一人で倒せるような奴じゃない」
「なんとかして見せる」
男が何かを思案しているような顔で言った。
「無理だって!」
九郎が怒鳴った。勝てるわけがない。実際に一度この男は奴にやられて死んでいる。
「『きんきらの仏様』のある場所を知っているか?」
「そんなものは無い」
突っぱねたが九郎は『きんきらの仏様』に心当たりがあった。
だが、折角助けたのにむざむざ死にに行かせるわけにはいかない。
「心当たりがあるんだろう、その言い方は。何もお前に戦えと言っているわけじゃない」
苦笑しながら的外れなことを言う男に九郎は焦れるような怒りを覚えた。
「なんでだ? なんでそんなことをする? あんた烏丸にも小菅にも関係無いだろ!」
男がほんの少し笑った。
「自分の為だ」
はにかんだような笑いだった。
「だから、お前が気に病むことはない」
「なんだよ……それ。意味が分からない」
助けてって言われたわけでもないのに。九郎には男の考えが分からなかった。
「途中まで案内を頼めるか。奴らに見つからぬうちに逃げて構わん」
男はまっすぐに九郎の目を見た。
「奴が恐ろしいのは分かる。だが、放っておけばまた犠牲者が出る。その子のように酷い目に会う子供が。俺はそんなものを見たくはない」
ぎょろりとした瞳に射られて、身動きができない。
だが、がらんどうの烏丸と違ってその瞳の奥には何かがあった。
つむじ風のように吹き荒れる、力強く暖かい何かが。

「だから、お前に助力を乞う。俺を助けてくれ」
九郎の中に男の言葉が落ちた。ずしりと胸が重くなる。
その重さにあえぐように九郎は言った。
「あんた、わかって言ってるんだろ」
男が意地悪く微笑んだ。
「簡単に他人に弱点をさらすな。付け込まれるぞ」
「いまさらな忠告ありがとさん。まさか覚えてるとは思わなかった」
「先ほど話したのだ、こんなにすぐには忘れられん」
「……くそ」
烏丸が怖い。
わざわざ殺されに行きたくない。
前回みたいに殴られるのも蹴られるのもまっぴらだ。
だけど、と九郎は思った。
「わかった。行く」
あんたには助けてもらったもんな。声にせずに呟いた。
「ただ、おれも手伝う。弱いけど、できる事ならなんでも、する、戦うのも」
「やめておけ、先ほどから震えているくせに無理をするな」
言われて気が付いた。いつの間にか全身が歯は鳴ってはいないものの震えている。
「怖いさそりゃあ! あんなおっかない奴を殺すなんておれには無理だ。死ぬ。絶対死ぬ!」
九郎は拳を自らの腿に打ち付けると、勢いよく立ち上がった。
「こうなりゃやけだ! 見ず知らずのあんたが戦うのに、村焼かれたおれが何もしないわけにいかないだろう!
村が好きだった爺ちゃんにも申し訳なさすぎる!」
突然立ち上がった九郎をぽかんと見上げた男が突然、おかしくてたまらないように噴き出した。
「……お前は、良い男だな」
「どこが!? 馬鹿にするな! それはあんたの方だろ!」
「馬鹿になどしてはいないさ。事実だ。お前、名は何という?」
「九郎だ」
「よろしく頼むぞ、九郎。俺は川上源(かわかみげん)次郎(じろう)小鷹(こだか)。小鷹で良い」
小鷹が右手を差し出した。
やけくそのまま乱暴に九郎がその手を掴んだ。
「頼むから何とかして見せてくれ。おれは死にたくないんだ」
「当然だ。俺も死ぬつもりはない」
小鷹の手は、岩のように固く暖かい大きな手だった。

*この小説はフィクションです。実在する地域の地名や伝承を使用していますが、登場する人物・団体・出来事などは架空の物であり、実在するものとは関係ありません。
*この小説は木曜日に更新されます。
前のエピソードを読む 第4話へ
次のエピソードを読む 第6話へ
筆者:藤田侑希
イメージ写真:井口春海、矢野加奈子