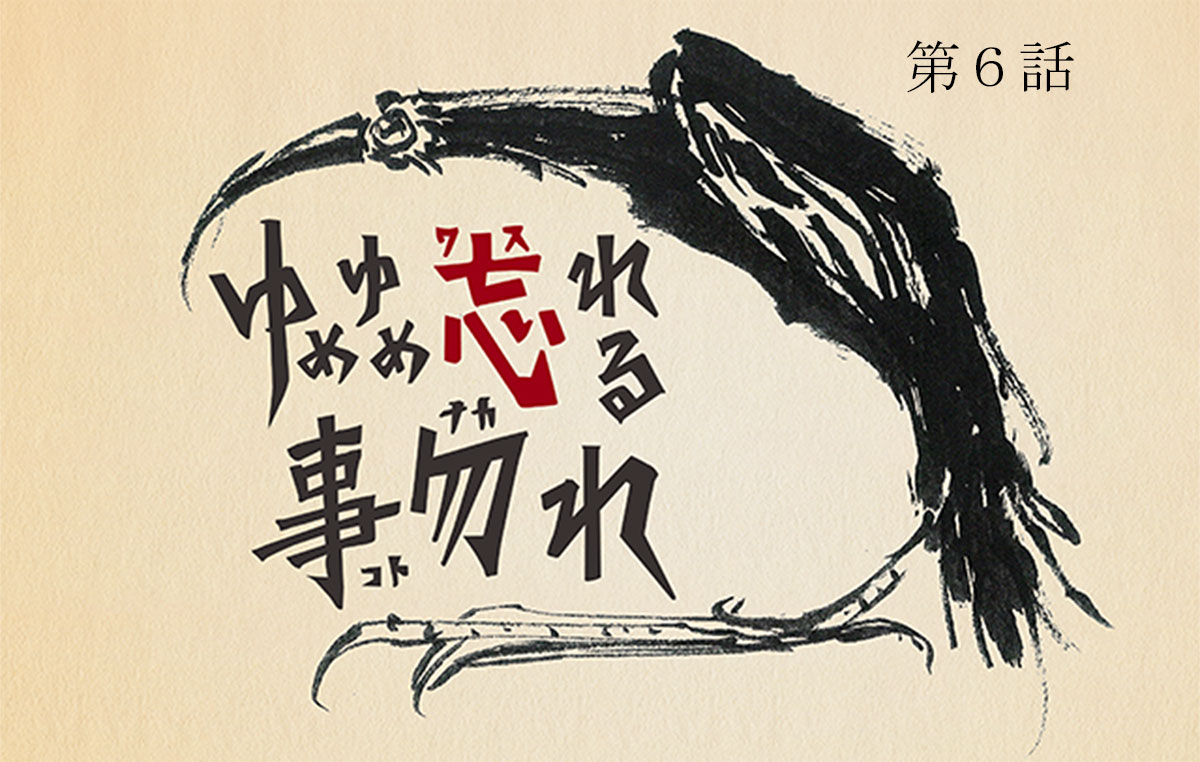この悲しみを繰り返さないために、九郎は小鷹とともに、烏丸を討つ事を決める。戦いの準備を進める中、九郎が聞いた小鷹の戦う理由とは。第二章終了、物語は第三章へ。
第1話はこちら→http://genryudaigaku.com/archives/6199
第5話はこちら→http://genryudaigaku.com/archives/6331
第二章 忘れることはできない
奥の間から、小鷹が紐でつながれた二つの包みと細長い布包みを持ってきた。
「念のために聞いておくが、人と斬り合いしたことは?」
「無い無い! ついでに言えば、がきの喧嘩で勝ったことも無い。毎回爺ちゃんに泣きついてた」
「見当がつくな。今でも頼りない体つきをしている」
「あんたと比べりゃ誰だって頼りないだろうよ」
自分の倍はありそうな腕を見て九郎は息をついた。
「そんな体してりゃ、村、守れたのかな」
「……いくら鍛えていようとも、精神が伴わなければ意味が無い。取っ組み合いに勝ったことが無かろうと、こういう場合においては戦い方なぞ幾らもある」
「なんか、爺ちゃんみたいなこと言うな」
九郎がガキ大将に殴られて泣いてるとき、爺様が似たようなことを言っていた。
いくら腕っぷしがあろうと、考えて使わないと意味がない。
「ほう。お前の爺様は分かっている方だな。戦いは肉体だけでするものではない。まあ、そうはいっても鍛錬はするべきだがな。鍛錬によって身体能力や技術だけでなく、判断力や精神力も身につくのだから」
小鷹が全ての包みをひらくと、刀と小刀が一振りずつと黒く丸い何かが十数個現れた。
その拳ほどの球体は十字に縄で縛られており、頭頂部の部分から縄が少し飛び出している。
「焙烙玉という。火をつけて投げると、破裂して金属片をまき散らす。お前でも十分人を殺傷できる威力はある」
陶器で出来た滑らかな焙烙玉の表面が、灯明の光を受けてなまめかしく輝いた。

「飛び出ている紐に火をつけて投げろ。あとで火口を貸してやる」
「わ、わかった」
「俺にぶつけぬように。それと」
小鷹が小刀の鞘を払って刃の確認をすると九郎に渡した。
分厚く短い刃が鈍く光っている。
「鎧通しという。名の通り鎧の隙間を狙って刺すための刀だ。お前がそれを使うことはなかろうが一応持っておけ」
「使いこなせる気がしないんだけど」
「お前がそれを使うのは最終手段だ。なるべくそうならないようにするさ」。
「頼むよ。お前だけが頼りなんだ」
九郎はおぼつかない手つきで刃を鞘に納めると、懐に小刀をしっかりとしまい込んだ。
胸元がずしりと重くなった。
「さて。作戦を練る前に、『きんきらの仏様』の場所について聞かせてくれ」
九郎の話を聞き終えると小鷹はいくつかの指示を九郎に与え、自らも支度を始めた。
薄明るい光の中、準備は着々と進んでいく。
「小鷹。戦うのは自分の為って言ってたけど、どういう意味なんだ」
九郎が、焙烙玉の入った袋を体に括りつけながら聞いた。
「そんなこと言ったか」
上がりかまちに腰かけて脚絆を巻いていた小鷹が聞き返した。
「言ったぞ。さっき話したばかりだ、こんなにすぐ忘れやしない」
してやったりとばかりに返す九郎に小鷹は呆れたように言った。
「つまらんぞ」
「聞かせてくれ」
小鷹が望んだとはいえ巻き込んだ以上、九郎はせめて理由が知りたかった。
何故自分に無関係なのにこうまで命を懸けられるのか。
小鷹は小さく息をついた。
「笑っていたのだ、あの子は」

「え」
「少し前にあった、大きな一揆を知ってるか」
「ええと、あんまり知らないけど、でかい一揆だったらしいな」
「一揆をおこしたのは、仏教徒の門徒たちだった。『進めば極楽、退けば地獄』を合言葉にしてな」
ぼんやりと向こうの障子を見つめる小鷹の瞳はどこか遠くを見ているようだった。
「俺は彼らを馬鹿だと思っていた。そんな言葉に命じられ戦わされている門徒たちを」
「それは言いすぎじゃないか? 一揆の人たちだって好きで戦ってた訳じゃないだろ」
小鷹は眉をひそめた九郎を見た。
「ああ、そうだな。本当に、そうだ」
ゆっくりと、噛みしめるように小鷹が言った。
「俺は何にもわかってはいなかったんだ」
小鷹の瞳の中に灯明の橙がちらちらと踊っている。
「武士だった時、一揆の門徒たちと戦った。彼らの城を兵糧攻めにしたのだ」
「……」
「どんな厚い信仰も空腹には勝てん。彼らは降伏した。だが、俺たちに下されたのは」
小鷹は言葉を切った。
「皆殺しの命だった」
「そ、んな、惨い」
「上は何度叩いても蜂起する彼らを恐れていたからな。やるならば徹底的だ。名の有る将たちが討たれたことへの復讐もあった」
「だからって、自分の国の人たちだろ」
小鷹がやり切れないように首を振り、二人の間を沈黙が満たした。
九郎は周りの薄闇が重さを増して背中にのしかかってくるように感じた。
「確か、ああ、そうだ。あの日は雨が、降っていた。冷たい雨と泥の中で、俺は彼らを斬った」
ややあって小鷹がその沈黙を破った。
記憶を確かめながら引き出すように、ぽつりぽつりと話し出す。
「子供がいた。骨と皮だけに痩せこけて、よろめきながら逃げていた。俺は、その子供を斬った」
何も言えず、ただ耳を傾けることしかできなかった。
「斬った瞬間、あの子供は笑っていた。安心したみたいに」
小鷹の声は掠れている。
「子供だけではない。男も女も、老人も沢山斬った。そのうちの誰かが言っていた、これで極楽に逝けると」

後悔と怒りと悲しみと、そして九郎には到底分からない感情たちが、煮詰められたような声だった。
「俺は恐ろしかった。彼らは馬鹿ではない。意思が無いのだ。あんなのは死人だ」
まるでその光景を見ているように、小鷹は目をかっと見開いている。
「そこで気づいた。俺自身もそうだと。俺も意思無く、言われるがまま彼らを斬った。彼らと何も違わない」
呻く様に話す小鷹へ、九郎はなんでもいいから何か言ってやりたかった。
だが役立たずの喉からは何も言葉が生まれない。
「今まで俺は死人だった」
感情が溢れた声と裏腹に、その顔は意外なほど穏やかだ。
その穏やかさはどこか諦めにも似ている。
「罪滅ぼしなのか?」
九郎は小さく聞いた。
小鷹が九郎の方へ顔を向けた。
目を眩しいものを見るように眇め、軽く口角を上げてすらいる。
「違う。俺は意思のない死人ではない、それを確認する。それだけの話だ」
「そうだったのか……」
九郎は鼻をすすりながら、爺様がいつも言っていた言葉を思い出していた。
『だれかを助けたいのなら、善き意思を持て。そうすればお前は望む奴を助けられる』
まだ意味はよく分かっていないが、小鷹の話に通じるような気がする。
小鷹は強いな、と思った。
もし自分が小鷹だったなら、何の疑問も抱かなかっただろう。そんな酷い戦からは逃げていたかもしれない。
「これでこの話は終いだ」

小鷹は少し面映ゆいように早口で言葉を切り上げ、立ち上がった。
「……おれ、小鷹みたいになりたいな」
気づけば小さくそう零していた。
怪訝と驚きの混じった顔で小鷹が振り向いた。
「やめておけ。俺なぞよりお前はもっと立派になれる」
「……まさか」
九郎は自分の手を見た。鍬で潰れたマメはあれど、小鷹よりも柔らかい手。
爺様に恩すら返せなかった、役立たずの手だ。
「いずれは、な。だがまずは今夜成すべきことを成そう」
小鷹は腰に刀を差しなおすと、古民家の扉を開け放した。
目が覚めるように明るい月の光が二人をさあっと照らした。
「今宵は満月。雲も風もない。絶好の戦日和だ。そう思わないか?」
小鷹がにっと笑った。
寝入っていた子供を起こし、朝までここにいるよう言い含めると二人は『きんきらの仏様』へと出立した。

*この小説はフィクションです。実在する地域の地名や伝承を使用していますが、登場する人物・団体・出来事などは架空の物であり、実在するものとは関係ありません。
*この小説は隔週木曜日に更新されます。
前のエピソードを読む 第5話へ
次のエピソードを読む 第7話へ
筆者:藤田侑希
イメージ写真:井口春海、矢野加奈子